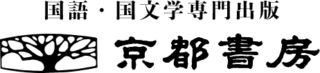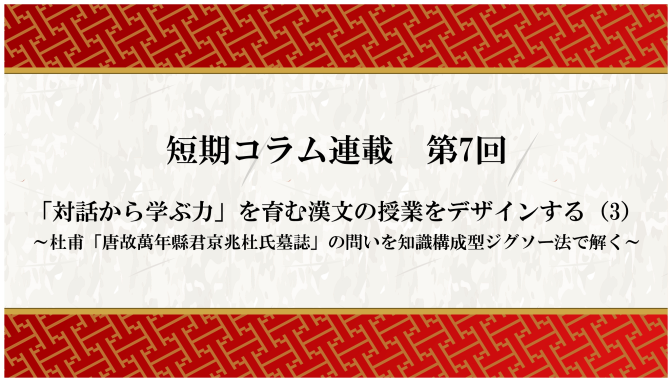※最終回となる今回は、前回のコラム「対話から学ぶ力」を育む漢文の授業をデザインする(2)の続編です。
コラムタイトルをクリックすると、前回のコラムをご確認いただけます。
それでは今回は、クロストークから報告を再開します。
クロストーク
呉三津田高校での知識構成型ジグソー法の授業の対象生徒は、理数探究類型(各学年1学級)の2年生・3年生74名。ラーニングコモンズに集めて、エキスパート活動・ジグソー活動ともに、18グループ(1グループ4~5人)での実施でした。
ジグソー活動を終え、クロストークに移り、各グループが3分程度発表しましたが、「我が子を犠牲に甥を救うことは義か」に対し、すべてのグループが「当時は義だったのだろう」と結論づけました。
しかし、前回挙げた生徒間対話の最後の発言にもあるように、どのグループも、忸怩たる思いや、考えれば考えるほどわからないことが出てくるものの、それを十分言葉にしきれない焦燥感に苦しんでいることも率直に述べました。
つまり、「それは、儒教社会の話だから」と前書きがつき、「一応納得はしたけど……」と但し書きがついたのです。その結果、クロストークは単なる発表ではなく、再び問いかけの場になり、次の三つの問いが生まれました。
・儒教社会では、「どちらの命を救うか」という究極の選択にも判断の価値基準が厳然として在る。現代のように、自己責任を問われるよりは、むしろ生きやすいのではないか。
・自分は生き残り、従兄弟は死んだという事実は、杜甫に罪悪感、トラウマを残さなかったのか。杜甫の詩に、それを探ることはできないか。
・授業で『孟子』の惻隠の心を習った。惻隠の心は仁の端というが、幼い我が子を見殺しにするのは、仁を実行できてないことになる。儒教社会の中でも矛盾が起きているのではないか。
これら新たな問いの出現は、知識構成型ジグソー法だからこそと言えます。複数のテクストを用い、幾重にも対話を組み込んだ今回の学習方法でなければ、単なる調べ学習を行うだけに終わっていたでしょう。
そして、この3つの問いは、次のパフォーマンス課題(小論文)のテーマとなり、この「対話的学び」の試みによって「深い学び」ができていたのか、一人一人について、客観的にその到達点を検証することへと繋がったのです。
パフォーマンス課題(小論文)で、一人一人の到達を見る
まず、「深い学び」について、中央教育審議会『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)』2016.12.21の定義を記します。
深い学び=習得・活用・探究という学びの過程のなかで、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、(ア)知識を相互に関連づけてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、(イ)問題を見出して解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう学び。
この定義に基づいて、呉三津田高校国語科教諭と協議して、パフォーマンス課題(小論文)を次の観点から評価しました。(〇は評価できる、●は評価できない)
①深い学び(ア)についての評価規準
・問いについて「義」あるいは「義ではない」との判断を、根拠を明確にして述べている。
〇与えられた4つの資料以上に、判断を支えるに強固な資料を新たに提示している。
〇与えられた4つの資料を批判的に再検討しそれに基づいて説得力ある判断をしている。
〇与えられた4つの資料に根拠を求めて判断している。
●資料の読解を誤っている。
・小論文(表現)の評価(①を表現の観点から見直した場合の評価規準)
〇関連する知識や考えをつないだ自らの筋道ができている。
●判断(結論)に至るために必要な知識や考えの説明が欠落している。
※①-●資料を誤読していても、筋道としては通りがよいものもあるが、やはりこれは評価できない。
②深い学び(イ)について
・小論文の方向性に関する評価規準
〇自分の先行経験をテクストの内容と結びつけたり、自分の知覚をテクスト内の人物やできごとと比較したりすることができている。
〇自分の反応を再点検し、評価することができている。
〇新たな問いを見出すことができている。
この評価基準に基づいて、私たちが高い評価をした小論文の一つを紹介します。
4つの資料から、当時の人々の目指すところは「世の安定」であることがわかる。歴史的に考えてみよう。『列女傳』は前漢末、成帝は趙飛燕・合徳姉妹に狂い、外戚の王氏一族が権力を握る中、漢の皇祖劉邦の末弟であった楚元王劉交の孫で、宣帝・元帝・成帝三代の天子に仕え、ご意見番を自負していた劉向が、衰退への危機意識を持ち、それを食いとめるために女の在り方を説いている書である。
『論語』も孔子の言行録であるから、時代は、春秋で、群雄割拠で不安定な社会状況下にある。「安寧」を求めれば、孝・弟という「不好犯上」が賞賛される。従って、我が子を犠牲にして甥を救った魯義姑や杜甫の叔母は、排行というルールに従う=革新(乱)を避け「安定」を守ったという結果から見れば、「義」である。
しかし、私は、この行為についての魯義姑の発言に注目した。「(もし我が子を優先したら)魯君は吾を畜はず。大夫は吾を養てず。庶民國人は吾に与せざるなり。」と言う。これが動機であるとすれば、自分が社会に受け入れてもらうために、子を犠牲にしたとも言える。自分への私愛だ。つまり、動機から厳密に判断すれば、「義」とは言えないことになる。私の中で、結論は出ない。
評価の理由は、資料2の孟子の母への追従=(孝)と、資料3の「順」は、資料4の「不好犯上」と言い換えることができ、その目指すところは世の安寧であり、一人一人がそれを認識して己の行為を決定することが、資料1の「公義」(公平な判断)であるとの理解に達していること。その上で、資料1を詳しく読んで動機に疑問を持ち、「正義は、結果によるか、動機か」と、次なる問いを導き出していることにあります。(※各資料については、前回のコラムを参照)
このことは、漢文が哲学資源となり得ることを立証しているのではないでしょうか。
知識構成型ジグソー法(学習者同士の対話(STEP. 2・3))における教員の役割
授業前の準備、授業中の観察及びファシリテーション
呉三津田高校での知識構成型ジグソー法の授業は、2019年9月20日と24日両日に行いました。
2019センター試験国語科第4問を解くことと、STEP.0・1までは、実施の2週間前までに同校国語科教諭によって行われていました。
9月20日、学習者はエキスパート活動に110分間かけて取り組みました。4日後の9月24日には、ジグソー活動とクロストークで130分。十分に時間をとりました。
対象生徒は理数探究類型の2年生・3年生でしたから、各グループに2年生・3年生が偏らないように、同校国語科教諭が配慮してくれました。(※各STEPについては、前回のコラムを参照)


また、会場になったラーニングコモンズには、筆者が提示した参考文献を授業の1ヶ月前から置き、放課後にブックトークが展開されることもありました。
このように、教員は授業前の準備に力を注ぎ、授業中のグループ活動には基本的に関与しない方が望ましいように思います。
授業は、同校国語科教諭1名と筆者がTTで授業を進め、他3名の国語科教諭がオブザーバーとして参加しました。
エキスパート活動では、複数の教員で観察していたため生徒の誤読にはすぐ気づきましたが、その場合も教員は正解を教え込むのではなく、グループの一人となって議論のレベルを上げるような、謂わばファシリテーターとしての参加を心がけました。
教員が誤読にじっくり付き合うことは、学習者の認知過程の躓きに気づき、授業改善のヒントにもなるのです。
一人一人が、問いに対する自分なりの答えを用意するために、漢文の資料を読み、持ち寄るエキスパート活動。この活動は、互いに自分の理解を外化し、対話の中に高め合うことを目指しています。
次のジグソー活動では、同じ資料を読んだ者はいません。つまり、今回は4つの資料を提供したので、4つの異なる形・色のピースで、自分たちなりに納得のいく答えを組み上げていくのです。
従って、教員は資料を提供するとき、どれか一つで答えになってしまうような資料を作らないことは心得ておかねばならないでしょう。
学習者達は、ジグソー活動で答えを作りながら、その答えが矛盾をはらむ、または視点を変えると別の側面が見えてくることに気づきます。
これが「対話から学ぶ力」であり、探究に向かう力なのだと考えます。
結びにかえて ―「対話から学ぶ力」を育む漢文教材―
このように、学習者の認識が更新したり、思索が深まった要因として、「良い問い」の設定があります。その「良い問い」を生み出す力が、漢文にはあるのではないかと筆者は考えています。
漢文は、そもそも政治に携わる「士大夫の言語」として、「読む」者に「歴史と自己のありかた」を「否応なく考えさせる」文体であったと言います。(1)
今、「哲学資源」としての漢文を学ぶことの意義も、まさにそこにあると言えましょう。(漢文は、一定の文法に従って読まねばならぬ異文化の文章です。従って訓読は、広く言えば翻訳であり、解釈であるのです。)
また、「中国の古典における物事の論じ方や描き方」について、吉川幸次郎は、「読みやすい漢文の文体(古代中国語)が成立したのは、紀元前6世紀から前3世紀頃で、所謂戦国時代であった。諸子百家が活躍した時代である。この創始の時期の文章は議論の文章が大多数であり、それが、現在に至るまでの日本漢文の祖である。」(2)と述べています。
つまり、私たちが読み継いできた漢文は、その文体において、すでにして議論に熱心な文章であると言えるのではないでしょうか。
議論の文章は、まず問いを立てることから始まります。
何を問うのか。例えば『論語』は、2500年の時を越えて今も生き続けています。それを読む人の受け止めによって異なりますが、短絡的な「答え」ではなく、「仁を問う」、「君子を問う」、「政を問う」など、人間存在及び人間社会への、真摯な「問いかけ」に満ちています。
漢字文化圏に生きてきた人々は、時代を超えて、常に『論語』と問いを共有してきたのです。古典として読み継がれてきた所以は、まさにここにあると言えるでしょう。
従って、このたびの授業でも生徒たちは、文脈を忠実に、丁寧に読むことを通して、普遍的な問いの発見に至っています。それは生徒にとって、漢文テクストが他者として向き合うに足る問いを持っていることの証左です。
かつて、江戸時代の寛政2年「寛政異学の禁」で、朱子学による解釈の一本化によって経書の素読に正解が定まってからは、それをマスターすると、読解と「会読」(対等で自由な討論)に進んでいました。
これも、漢文の持つ「問い」が実現せしめた、一つの「学び」のスタイルであると考えます。
7回にわたって、教育実践・研究について発表する場を提供いただいたこと、また、お読みくださった皆様に感謝します。
今後も、漢文教材を「哲学資源」という観点から捉え直し、その学習に最も適した「会読」(講学)を、アクティブラーニング(以下ALと記す)として再検討するという、新たな深い探究的な学びを可能にする漢文教育の提案をしていきたいと考えています。
さらに漢文の異文化としての側面から、グローバル社会で自・他を相対化し、真摯に向き合って、新しい答えを作り出す力を身につけた生徒・学生の育成に資する漢文プログラムを開発することを目指し、その際机上の空論とならないように、教育現場(高等学校)や教育委員会、大学(教員養成)と緊密に連携して、そのプログラムの有効性・可能性を検証し、汎用性のあるものとして構築したいと臨んでおりますので、どうか御指導・御鞭撻の程、よろしくお願いします。
(1) 齋藤希史は「漢文は士大夫の言語でしたから、それを読み書きするうちに自己をそこに重ね合わせ、歴史上の士大夫がどうであったか、自らはどのように歴史に参与すべきか、否応なく考えさせられるのです。漢文に特有の思考や感覚や議論が、漢文という文体を用いることと不可分のものであることは明らかでしょう」と、漢文という文体が、人に否応なく考えさせる文体であったことを説明している。(『漢文脈と近代日本』角川文庫 2016、p.99-100)
(2) 吉川幸次郎『漢文の話』ちくま文芸文庫 筑摩書房 2006、p.97
———————————————
国語・国文学専門の教育出版社
株式会社京都書房
https://www.kyo-sho.com
———————————————