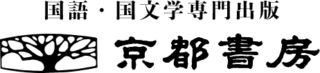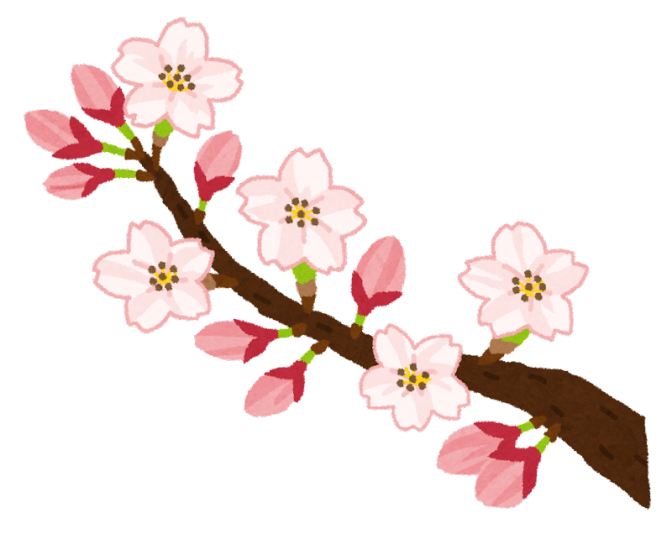T・Nです。今年は例年になく桜の開花が早く、京都市内の桜は4月早々にして、葉桜へと装いを変えつつあります。
桜といえば、「花は桜木、人は武士」という諺にもあるように、日本では武士(侍)の生きざまを桜の花に喩える伝統がありました。
WBC侍ジャパンの快挙も発奮材料としつつ、新年度以降も、武士道精神で気高く粛々と(?)業務に邁進して参ります。
さて、本日は京都書房が1970年(!)以来刊行を続けているロングセラー商品・『過程の演習 新国語問題集』(以下、新問)について、お話させていただきたいと思います。

同シリーズの製作にあたっては、例年国語指導のエキスパートたる現場の先生方を一堂に集め、討議のもとで良問を厳選していただき、設問を解く「過程」がしっかり身につく丁寧な解説・解答原稿を頂戴しています。
今回はこの、由緒正しき(?)過去の『新国語問題集』に掲載された作品のうち、個人的に印象に残っている文章を、パブリック・ドメインの作品に絞って2点ピックアップしたいと思います。
①「三人の訪問者」島崎藤村(『新問 第26集』p.47-48)
「貧」が訪ねて来た。
子供の時分からの馴染のような顔付きをしたこの訪問者が、復た忸々しく私の側へ来た。
(中略)
よく私に清いという言葉をつけて、「清貧」と私を呼んでくれる人もあるが、ほんとうの私はそんな冷かなものではない。私は自分の歩いた足跡に花を咲かせることも出来る。私は自分の住居を宮殿に変えることも出来る。私は一種の幻術者だ。こう見えても私は世にいわゆる「富」なぞの考えるよりは、もっと遠い夢を見て居る。」
上に掲げたのは、京都大学(前期日程)入試問題として掲載された短編のなかの一節です。
「冬」「貧」「老」という概念そのものを疑人化し、それぞれが「私」と対話をかわしていくという寓話的な筋立てとなっています。
(中略)以降の箇所は、「貧」が「私」に対して語りかけているせりふの後半部分にあたり、「ほんとうの私はそんな冷かなものではない。」以降の、「貧」(=貧しさ)に対する一般的な先入観を打ち消す内容は、作品発表から100年以上経過した現在の視座から見ても、新鮮かつ重く受け止めるべきテーマを投げかけているように感じられます。
②「雪解(ゆきげ)」横光利一(『新問 第37集』p.54-55)
卓二はそう云いつつも、一年の間に、傍にいるに拘らず、ひと言も栄子に話せぬ情態になってしまっていることが、ひどく切なく苦しかった。しかし、栄子も卓二も噂の渦中に立ちあわせた他所他所しさで、最後のこの時さえ、まだどちらからともなく視線を脱しあうのだった。
間もなく、栄子は隣家の女中と一緒に店を出ていった。卓二はよほど時間がたってからその方を向いてみると、角の黒いポストの影に姿を隠した栄子が、まだこちらを向いて立っていた。
(中略)
それでも、ポストと一本になって立っている栄子の影は動き出す様子もなかった。卓二は今もなおそこから去っていった栄子の姿を思い出すことが出来ない。店へ入ってから卓二は歯の抜けた店主に久しぶりの挨拶をした。そして、半年前の夜のように店頭から秘かに表の方をうかがうと、ポストは今もあり、その影も横町へ深く曲り込んでいる町影と一緒に溶けあって、長くずっと栄子の家の方へつづいていた。
卓二は煙草を買って外へ出てから、栄子がしたままの姿勢でポストの前に立って見た。そこの影の中からは店の灯を浴びた中の様子がはっきりと手に取るように見られた。それは闇でもなく影でもない、光に生きた明るい世界ばかりだった。
彼はポストの口に片手をさし入れてみて、そこからどこか分らぬ遠い所へ手紙を出してみたいと思った。
こちらは、奈良女子大学(後期日程)で出題された入試出題文の末尾にあたる部分です。
十七歳になった主人公の卓二は、十四歳の栄子に思いを寄せますが、卓二が東京へ働きに出た年の「秋の暮」、栄子がスペイン風邪で亡くなったという一報が舞い込みます。
作中の時系列でみると、東京へ発つ前夜に「栄子の姿を最後に見た」時の回想から、視点が現在(卓二が栄子と過ごした「町」に戻って在りし日の栄子を追憶している状況)に移動する前後の箇所にあたります。
文章の美しさもさることながら、横光利一自身の実体験が下敷きになっているという背景も加味すると、細部の描写が一層の痛切さを伴いながら迫ってきます。
ところで、昨今の教育現場では、新カリキュラムの枠組みの中で「文学をどう教えるか」というテーマについて、頻りに議論が交わされているとの話も漏れ聞こえてきます。
かつては英語科の教科書にも文学作品が豊富に掲載され、教科書を通じて文学を学ぶ機会が一定程度担保されていました。
しかし、現在の英語教科書は、掲載コンテンツの大多数が、説明的文章やダイアローグ形式のテキストに占有(?)されているのが実情です。
辛うじて文学作品を排除することなく踏みとどまっている国語科は、ともすれば、学校で文学を学ぶ最後の砦となっている側面も認められるのかもしれません。
私事ではありますが、かつて大学入試センター試験 (大学入学共通テストの前身)の英語過去問を解いていた際に、例えば以下に示すような美しい表現に出会ったことで、苦痛で仕方なかった勉強の途上に、ささやかな充足感を見出すことができました。
He found contentment beside the slow-moving water, which, like himself, had left the steep, rocky days far behind.
――1998年度センター本試験 第6問
(彼はゆったりとした水の流れの傍で――その川が、彼と同じく険しい岩間を進む急流であった過去の日々を遥か後方に遺してきたことによる――満足を見出した)
The music seemed to descend from out of the night itself.
――1998年度センター追試験 第6問
(その調べは、夜の深淵そのものから降りてくるかのごとく思われた)
心なしか、最近の入試問題には、このように心を揺さぶられる(あるいは、出題者による教育的配慮の下で供される)文章素材が少なくなったように感じています。
当方のような立場で申し上げるのもおこがましい限りですが、学校採用教材に掲載された作品が、後の人生にあって、人間の尊厳や気高さを感じられる文学との出会いをもたらす”触媒”になることを、願ってやみません。
近刊の『過程の演習 新国語問題集 第 54集』では、長きにわたる『新問』の伝統を汲み、国公私立の先生方が選りすぐった良質な「文学素材」も豊富に掲載されます。
教育現場に良質な読書経験をもたらすメリットをもご考慮の上、『新問 第54集』のご採用を前向きに検討いただきますと幸いです。
———————————————
国語・国文学専門の教育出版社
株式会社京都書房
https://www.kyo-sho.com/
———————————————